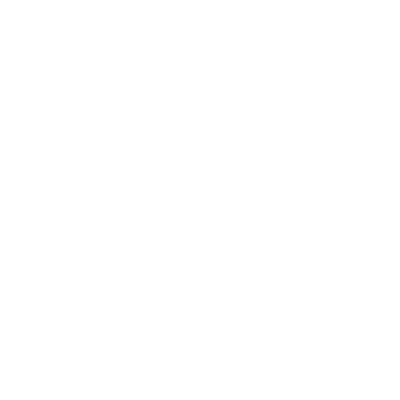子どもの頃、「独自ルールの遊び」をした記憶はないだろうか?
私はよく、友達と自分たちだけのルールで野球をしていた。
それを思い返すと、この「遊び」の中に、建築を考えるうえでの大切なヒントが詰まっていたように思う。
校庭のすみっこで生まれた“僕らの野球”
あれは小学校4年生の頃だった。
僕らは、広い校庭のはじっこを使って、独自ルールの野球をしていた。
一塁は電柱、二塁は向こうのポール、三塁はタイヤの遊具。
ホームランは、クリティカルヒットでしか届かない柵に当たること。
校庭にあるモノすべてを、自然と遊びの中に取り込んでいた。
ルールは毎回、みんなで話し合って決めた。
きっちり整備されたグラウンドにも憧れはあったが、
この即興的で場に根ざした野球は、それとは比べられない面白さがあった。
制約が生み出す創造性
ボールは紙をラップで巻いたもの。
バットはペットボトル。
場所も狭く、特別なものは何もない。
でも、その制約こそが創造の出発点だった。
環境をどう遊びに取り込むか、道具をどう工夫するか。
限られた条件の中でこそ、自分たちだけのルールと空間の使い方が生まれていった。
身体と場所がつながる感覚
いま思えば、
四年生だった僕たちの身体感覚にぴったりだった。
紙ボールの重さも、ペットボトルのバットの扱いやすさも、
電柱からポールまでの走れる距離感も、
すべてが身体と地形のスケールに合っていた。
その遊びには、道具と場所と身体が一体になるような快さがあった。
建築もまた「独自ルールの遊び」かもしれない
建築もまた、そんなふうに場の特性を見つけて取り入れる行為であっていいのではないか。
与えられた条件や制約の中で、
それをネガティブに捉えるのではなく、
“面白さのきっかけ”として扱う発想。
そして、建築という“ルール”を下敷きにしながらも、
その土地、その人、その暮らしにふさわしい
「オリジナルのルール」を見つけていくこと。
子どもの頃の遊びのように、
建築もまた、自由に、楽しみながら考えていい。
誰かが決めたルールに倣うだけでなく、
目の前にある環境や、その場に流れる空気を読み取りながら、
「ここだからこそ」のかたちを見つけていくこと。
そうして生まれた建築には、
きっと、あの頃感じていたような、
身体と空間がつながる快さや、誰かと分かち合う楽しさが宿るはずだ。