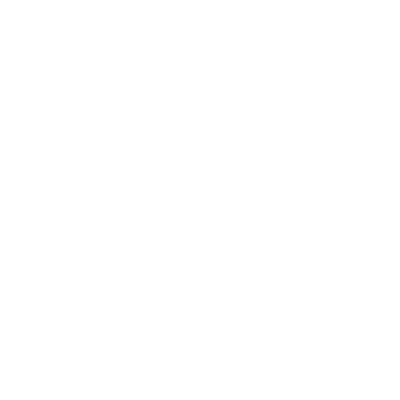ストリートからはじまる建築|バンコクの街に学ぶ都市の魅力
タイ・バンコクの街を歩いていて、強く印象に残ったのはストリートの自由さでした。
店舗がひしめき合い、人々が行き交い、集まり、くつろぐ。
ストリートが生活の一部として、日常のなかに自然に溶け込んでいる様子に、驚きと魅力を感じました。
市場で食材を買い、そのまま路上で食事をする。
椅子や机が並び、人が腰掛け、笑い合う。
その風景には、都市と暮らしが近い距離で重なり合っている実感がありました。
ストリートは「共有される居場所」
ストリートは、特定の誰かのものではない、公共の空間です。
都市に住むみんなでシェアし、活用している“共有の居場所”とも言えます。
だからこそ、そこにはいくつもの時間と領域の重なりが生まれます。
-
都市が持つ構造的な時間
-
偶然そこを行き交う人々の時間
-
そして、私自身がそこで過ごす個人的な時間
こうした都市・社会・個人の交差点のような場所が、文化を凝縮し、都市の魅力へとつながっているのだと感じました。

境界のない風景がつくる“重なり”
驚いたのは、線路のすぐ隣で人々が食事をしていた風景です。
線路とストリートとの間に、明確な境界がない。
日本ではなかなか見られない状況ですが、そこには都市の重なり方の可能性が見えました。
もちろん安全面の配慮は必要ですが、
「線路のすぐ脇でくつろぐ」という体験は、日常の中に非日常を持ち込むような、新鮮な魅力があります。

生きている市場、変化する場所
ストリートからつながる高架下に広がる市場にも足を運びました。
日本にも高架下空間はありますが、タイの市場にはエネルギーの質が違うと感じました。
市場は時間によって様子を変えます。
準備が始まったかと思えば、1時間後には人がどっと集まり、
終わるとすぐに片付けられて、元の広場へと戻っていく。
その様子はまさに、都市の中でリアルタイムに呼吸する空間でした。
そんな市場で食べたご飯は、単なる食事以上の、都市体験としての特別さを感じさせてくれました。
ストリートと建築の新しい関係
日本の都市では、敷地境界線の意識が強く、
ストリートとの関係性がどうしても希薄になりがちです。
プライバシーや防犯の課題もありますが、
それでも、ストリートの可能性を見つめ直すことで、建築と都市の関係をもっと豊かにできるのではないかと思います。
バンコクのように、ストリートが日常と交差する場所として機能するなら、
建築はもっと開かれた存在になれるのではないでしょうか。
ストリートの観察から、建築と都市が重なり合う新しい関係性をつくっていく。
そんなヒントを、バンコクの街がそっと教えてくれた気がします。