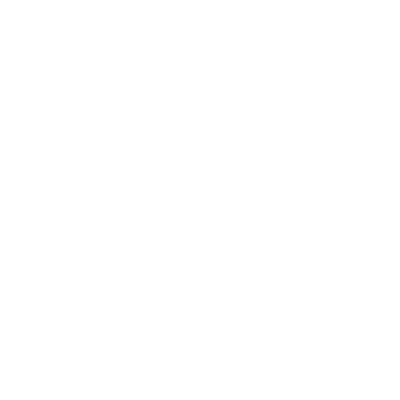廃墟のような空間に惹かれる
廃墟には、空間からの“押し付け”がないと感じます。
かつての用途や機能は時間とともに薄れ、ただ「空間」として残っている。
その役割を失った場所が、なぜか人を惹きつけるのは、そこに本来の自由さが表れているからではないでしょうか。
私たちの日常は、強い意図に基づいた空間に囲まれています。働く場所、学ぶ場所、休む場所——。
こうした「目的ありき」の環境に慣れているからこそ、
廃墟のように規定から解き放たれた空間に立つと、心がほぐれる感覚を覚えるのではないでしょうか。
廃墟は建築ではない、けれど建築とつながっている
廃墟は、人の手によってつくられた構造物でありながら、自然の作用を受けて変容した存在です。
草木に覆われ、風雨にさらされながら、かつての痕跡だけが残る姿は、もはや「建築」とは呼べないかもしれません。
建築とは、本来、人間の意図に基づき設計されるものだからです。
けれども、その「建築でないもの」の中にこそ、空間の本質が垣間見えることがあります。
意図が過度に強ければ、空間は一方的な使われ方しか許さなくなる。
「ここはこう使うべきだ」と決められた場所に、かえって居心地の悪さを覚えた経験は、多くの人が持っているはずです。
廃墟は、意図を超えて存在することで、空間が持ちうる自由さを私たちに示しています。
空間と機能の“ギャップ”に可能性がある
建築は生活の器であり、機能を満たすことが第一に求められます。
しかし同時に、空間と機能が必ずしも一致しないとき、そこに新たな可能性が生まれます。
「この場所を、こう使ってもいいのではないか」
「こんなふうに過ごすこともできるかもしれない」
そうした想像を促す余白のある空間は、人を主体的に関わらせ、建築に“楽しさ”や“自由”を与えます。
使い方が一つに定まらないからこそ、「自分なりに使ってみたい」と思わせる。
そのとき空間は、単なる機能の容れ物を超え、魅力を持つ存在になるのだと思います。
廃墟が教えてくれる時間的な奥行き
建築家ルイス・カーンは「よい建物は、素晴らしい廃墟を生みだす」と語りました。
この言葉は、建築が時を経てもなお魅力を失わないこと、そして廃墟に至っても秩序や美しさを保ち得ることを示しています。
廃墟は、建築の終末ではなく、時間の中で現れるもう一つの相貌です。
建築と廃墟は切り離された対極ではなく、連続する関係にある。
そして、そのあいだに広がる「余白」こそ、これからの空間づくりを考える上で大切な手がかりになると考えています。