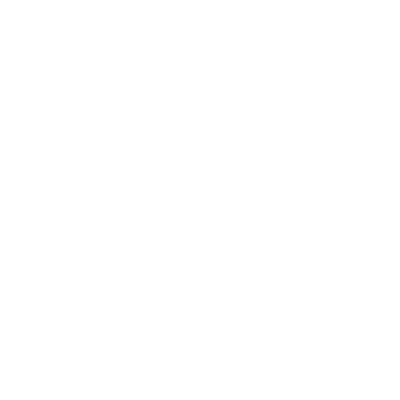思考のスケッチ
建築には約20年ごとに、「動物的」な感性――生物のようなかたちやふるまい、環境への適応性など――が姿を見せる周期があるという切り口。メタボリズム、動的曲面、パラメトリック、そしてポストAIへと続く系譜をたどりながら、建築と生命の関係を振り返る小さなスケッチ。
まちの魅力は、時間や営みの「重なり」によって形づくられることが多くあります。ヴェッキオ橋のように、構造・用途・歴史が積層することで独自の空気が生まれます。建築においても、既存の場に新たな行為を重ねることで、その場所らしい空間が立ち上がります。重なることは、関係性をつくること。そこに、日常が自然と溶け込むような設計の手がかりがあると感じています。
子どもの頃、独自ルールで遊んだ経験には、建築を考えるヒントが詰まっている。限られた道具や場所を工夫し、即興的にルールをつくる遊びは、身体と場所が自然につながる感覚を生んでいた。建築もまた、制約を創造のきっかけとして捉え、その土地や人に合った“オリジナルのルール”を見つける行為かもしれない。誰かが決めた枠にとらわれず、自由に、楽しく、場所と向き合う姿勢が建築の魅力を深めてくれる。
建築の選択に迷ったとき、「それはよろこびにつながるか」をひとつの指標にしています。
素材やかたちの背景にある感覚を見つめ直すことで、その人らしい居場所が見えてくる——そんな思考の記録です。
建築を考えるうえで大切にしているのが「境界」と「定着」というふたつの視点です。柱や壁などによって空間の輪郭=境界が生まれ、そこに“居たい”と思わせる何かがあると人は定着します。それは安心感のある形や手触り、静かに引き寄せられる存在かもしれません。自然の中にもこの関係性は見られ、心地よい建築は境界と定着が調和しているものです。そうした感覚を丁寧に積み重ねることが、魅力ある空間につながると感じています
都市は多様な人工物が重なり合ってできており、その交差から思いがけない魅力や風景が生まれます。異なるスケールやルールが共存する都市の姿は、建築にも応用できるヒントです。すべてを整然と整えるのではなく、重なりを受け入れることで、予期せぬふるまいや新しい体験が生まれる空間が生まれる。そうした設計は、多様な価値観が混在するこれからの時代にふさわしい建築の在り方だと感じています。
窓は単なる開口部ではなく、内と外をつなぐ“出会いの場”として空間に豊かさをもたらします。光や風、景色との関係性が生まれることで、窓辺は人が自然と集まる居場所になります。特に古民家再生では、窓辺は生活と風景のあいだに新たな関係をつくり、日常の中に豊かなふるまいや時間が生まれていきました。どのように窓を設け、そのまわりにどんな行為が生まれるか——そこに建築をかたちづくる本質的な問いがあると感じています。
廃墟には、機能や役割を失った空間ならではの自由さと引力があります。強い意図に縛られない空間は、人の想像力を解き放ち、建築に必要な“余白”の大切さを教えてくれます。建築と廃墟、そのあいだにこそ、空間の本質的な魅力と可能性があるのかもしれません。